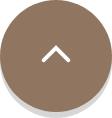目次

不動産相続に
必要な費用と書類
不動産を相続した経験がある方は限られるため、「どのような費用が必要になるか」「どのような書類を用意しなければならないか」などについて把握していない方も多いのではないでしょうか。こちらでは、実際に直面した場合にスムーズに進められるよう、不動産相続に関する費用や必要な書類、贈与税の算出方法などについて解説します。
Point不動産を相続した際に
発生する税金、費用とは?

家屋や土地などの不動産を相続した場合、どのような費用負担が生じるか知っておくことが大切です。中でも、負担が大きくなりがちなのが相続税。ほかにも、登録免許税をはじめ、必要書類の取得費用、税理士や司法書士への手数料などを支払わなければなりません。こちらでは、不動産を相続した場合に生じる費用とその目安について紹介します。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 税金・費用 | 概要 | 負担額の目安 |
|---|---|---|
| 相続税 | 財産が基礎控除額を超える場合に発生します | 財産の総額が、基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)を超えなければかからない 控除分を超える額に応じて、10%~55%の税金 |
| 登録免許税 | 相続登記(不動産の名義変更)にかかる税金 | 固定資産税評価額×0.4% ※例外的に2.0%の場合も |
| 必要書類の取得費用 | 主に登記手続きに必要な書類を取得するための費用 | 登記手続きに必要な書類すべてで約3,000円~ |
| 税理士や司法書士への手数料 | 相続税の申告や相続登記の手続きを依頼した場合の手数料 | 5~10万円程度 |
Point贈与税とその算出方法について

贈与税は、父母から子ども、配偶者同士、祖父母から孫など個人から個人へ財産を渡した際に生じる税金です。毎年1月1日から12月31日までの間に受け取った金額を基準に算出されます。贈与税の対象となる財産は、金銭はもちろん、不動産や有価証券、貴金属なども含まれます。また、住宅ローンの支払いや借入金返済を肩代わりしてもらう、適正価格よりも安く不動産を購入したといったケースでも贈与税が生じることがあるため、注意しなければなりません。
不動産贈与における贈与税の算出方法は、「(不動産の価格 − 基礎控除額)×税率 – 控除額」です。贈与税の基礎控除額は一律110万円と定められています。税率や控除額は不動産価格から基礎控除額を差し引いた額で変動するため注意すると良いでしょう。また、税率には「一般贈与財産の税率」と「特例贈与財産の税率」の2種類があり、それぞれの以下のような違いがあります。
【一般贈与財産の税率(一般税率)】
親族以外の方々や夫婦間、兄弟姉妹間、そして親から未成年の子どもへの贈与の場合、税金の計算には「一般贈与財産の税率」が使われます。この税率は、贈与の関係性や受け取る側の年齢に関わらず、広く適用される基本的な税率です。
つまり、特別な関係性や条件がない限り、多くの贈与ケースでこの税率が適用されることになります。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 〜200万円以下 | 10% | なし |
| 200万円超〜300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超〜400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 500万円超〜600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超〜1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超〜1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 1,500万円超〜3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超〜 | 55% | 400万円 |
【特例贈与財産の税率(特別税率)】
親や祖父母など、直系の年長者から成人した子や孫への贈与には、特別な配慮がなされています。このような場合、通常の贈与税率ではなく、「特例贈与財産の税率」が適用されます。この特例税率は、世代間の財産移転を促進し、若い世代の経済的自立を支援する目的で設けられています。
つまり、親から成人した子へ、または祖父母から成人した孫へ財産を贈与する際には、より有利な税率で計算されることになり、贈与を受ける側の税負担が軽減される仕組みとなっています。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 〜200万円以下 | 10% | なし |
| 200万円超〜400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円超〜600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 600万円超〜1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,000万円超〜1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 1,500万円超〜3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 3,000万円超〜4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超〜 | 55% | 640万円 |
上記をふまえて、1,500万円の不動産を贈与された場合の算出方法は以下の通りです。
一般贈与財産の税率
1,500万円(不動産価格) – 110万円(基礎控除額) = 1,390万円(課税価格)
1,390万円 × 45% (税率)= 903.5万円
903.5万円 – 175万円 (控除額)= 728.5万円
贈与税は、728.5万円になります。
特例贈与財産の税率
1,500万円(不動産価格) – 110万円(基礎控除額) = 1,390万円
1,390万円 × 40%(税率) = 834万円
834万円 – 190万円(控除額) = 644万円
贈与税は、644万円になります。
また、20歳のときに第三者と祖父から贈与があった場合、贈与税は一般贈与財産の税率と特例贈与財産の税率を併用して算出することになります。例えば、第三者から500万円の土地、祖父から1,000万円の建物を贈与された場合の計算方法は以下の通りです。
一般贈与財産の税率
1,500万円(土地と建物を合算した不動産価格) – 110万円(基礎控除額) = 1,390万円
1,390万円 × 45%(税率) = 903.5万円
903.5万円 – 175万円(控除額) = 728.5万円
728.5万円 × 500万円(土地の不動産価格) / 1,500万円 = 242.83万円
特例贈与財産の税率
1,500万円(土地と建物を合算した不動産価格) – 110万円(基礎控除額) = 1,390万円
1,390万円 × 40%(税率) = 834万円
834万円 – 190万円(控除額) = 644万円
644万円 × 1,000万円(建物の不動産価格) / 1,500万円 = 429.33万円
贈与税は一般贈与財産の税率での242.83万円と、特例贈与財産の税率429.33万円を合算して、672.16万円になります。
贈与税の計算方法について正しく理解しておくことで、贈与を受けた際に慌てず対処できるようにすることが大切です。
Point不動産を相続した際に必要な書類について

相続登記には、戸籍謄本や印鑑証明書、固定資産評価証明書など多くの添付書類が必要です。また、「遺言書の内容に沿って相続した」「遺産分割協議によって相続した」「法定相続分通りに相続した」など、それぞれのケースで申請書類が異なるため、注意しなければなりません。相続登記をスムーズに進めるためにも、早めに準備を進めましょう。
相続登記に必要な書類
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 登記手続きに必要な主要書類 | 取得できる場所 |
|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 | 本籍地の市役所 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | |
| 被相続人の住民票の除票 | 各居住地の市役所 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | |
| 不動産を相続する相続人の住民票 | |
| 固定資産評価証明書 | 相続する不動産の所在地の市役所 |
| 登記申請書 | 自分で作成(申請書様式:法務局) |
| 遺産分割協議書 | 作成が必要 |
相続税の申告手続きは当窓口にご相談ください

相続税の申告は、相続財産が基礎控除額を超える場合に必要です。相続税の申告は煩雑な上、戸籍謄本や遺産分割協議書の写し、相続人すべての印鑑証明書など多くの添付書類も用意しなければならないことから、8割以上の方が税理士に依頼していると言われています。当窓口は税理士と連携し、相続税の申告を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
Point「不動産相続に困っている」という方は、
金沢市・かほく市~白山市での
実績が豊富なかなざわ相続の窓口へ

かなざわ相続の窓口は、不動産相続に強みを持つ不動産会社です。金沢市を中心に、かほく市、野々市市、白山市、津幡町、内灘町で、実績を積み重ねてきました。当窓口は、司法書士や行政書士、土地家屋調査士、税理士などの専門家と連携しており、生前対策から相続後までのご相談に対応可能です。不動産相続についてのお悩みは、かなざわ相続の窓口までお問い合わせください。