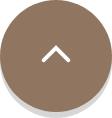目次

知っておきたい相続についての基礎知識・やるべきこと
自身の財産を残す、親から財産を引き継ぐといった相続は、あらゆる人が経験します。その際、家族や親族の間で大きなトラブルが起きないためにも、事前に相続について理解することが大切です。こちらでは、不動産の相続についての基礎知識や流れに加えて、相続登記の義務化といった役立つ情報をお伝えします。
Knowledge相続の基礎知識

相続とは?
相続とは、人が亡くなった際に、その方の財産や権利・義務を家族などが引き継ぐ仕組みのことです。この仕組みの中で、亡くなった方を「被相続人」、財産などを引き継ぐ方を「相続人」と呼びます。
相続に関する基本的なルールは民法で定められており、これらをまとめて「相続法」と呼ぶこともあります。相続法では、以下のような重要な点が定められています。
- 誰が相続人になるのか
- どのような財産が遺産として扱われるのか
- 被相続人の権利義務がどのように引き継がれるのか
これらのルールによって、相続の過程が公平かつ円滑に進められるよう定められています。相続は家族にとって大切な出来事であり、法律に基づいて適切に処理することが重要です。
Pick up
2024年4月1日から
相続登記が義務化されています

不動産を相続した際、その名義を被相続人から相続人へと変更するための申請を相続登記と言います。これまでも相続登記は申請しなければなりませんでしたが、期限や罰則がなかったため、そのまま放置しているケースが散見されていました。そのため、法改正によって2024年4月1日から義務化されました。
1. 相続登記の義務化が対象となる方とは?
相続登記の義務は、不動産を相続した方のみが対象になります。たとえば、家屋やアパートなどを親から相続で引き継いだ場合です。相続登記の申請期限は3年以内と定められており、そのカウントが始まる日は、相続のケースによって異なります。
・不動産を相続した場合、その所有権の取得を認識した日から3年以内
・不動産の遺産分割が確定した場合、確定日から3年以内
・令和6年4月1日以前に不動産の相続が開始されている場合、相続開始日から3年以内
2. 2024年4月1日以前に相続した不動産も対象になります
2024年4月1日の施行日以前に相続した不動産についても、相続登記の義務が適用されます。この場合、相続登記の期限は、改正法の施行日、または不動産の相続を認識した日のうち、遅いほうの日から3年以内です。
3.3年以内に相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が科されます
正当な理由がなく3年以内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料を科される恐れがあるため注意が必要です。ただし、以下のようなケースでは、正当な理由として認められる可能性があります。
・複数の相続人がいるため、相続登記に必要な資料を収集する時間を要する
・遺産の範囲や遺言の有効性について争いが起きている
・相続登記を申請すべき人が重い病気を患っている
・相続登記を申請すべき人がDVによって生命や心身に重大な被害を受ける恐れがある
・経済的な困窮から、相続登記を申請するための費用を負担できない
上記のような理由がない場合は、過料を科されないためにも、相続後3年以内に相続登記を行いましょう。

認知症の方は、不動産関係の
契約がすべて認められません
認知症を発症した場合、医師から「認知機能や判断力が低下している」と診断されるため、民法上、この状態での契約行為はすべて無効になります。当然、不動産の売買や賃貸借契約の締結なども例外ではありません。そのため、認知症によるリスクをふまえて将来的な財産相続に備えることが大切です。
日本では、65歳以上の6人に1人が認知症を発症しています。もし、財産を所有している方が認知症になってしまった場合、以下のような手続きができずに、遺産分割協議で相続人同士の争いが起きるかもしれません。
認知症になるとできなくなること
- 預金の引き出しや解約
- 契約に関わること
- 不動産の売買
- 相続税対策
- 遺言書の作成や遺産分割の検討
財産を所有している方が認知症と診断された場合であっても、「成年後見人制度」や「家族信託」を活用することで、不動産の契約を進めることが可能です。
Knowledge相続手続きの流れとやるべきこと
STEP
01
なるべく早く~7日以内
- 「死亡届」を提出する
- 各種口座(銀行、証券など)や公共料金などの解約、名義変更をする
遺言書を確認する
相続手続きをスムーズに進めるためには、まず遺言書の有無について確認することが大切です。多くの場合、遺言書は、自宅や銀行の貸金庫、法務局、公証役場などで保管されています。遺言書が見つかった場合は、速やかに家庭裁判所に提出し、検認の手続きを行わなければなりません。勝手に遺言書を開けてしまうと、5万円以下の過料を科される恐れがあります。検認を通じて、相続人に遺言の存在と内容を知らせるだけでなく、遺言書の形状や内容を明確にすることで、偽造や変造を防ぎます。なお、検認の対象となるのは被相続人自身が管理していた「自筆証書遺言」です。公正証書遺言や法務局で保管されている自筆証書遺言については、検認は必要ありません。
STEP
02
10日以内
- 「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出する
相続人を確定する
相続を行う前に、相続人を確定させる必要があります。相続の完了後、相続人が漏れていることが判明した場合、遺産分割協議をやり直さなければいけません。また、遺言執行者がいる場合、すべての相続人に財産目録を交付する必要があるため、相続人を確定させなければならないのです。
相続人を正しく確定させるためには、被相続人が生まれてから亡くなるまでのあらゆる戸籍謄本を確認する必要があります。仮に、被相続人に離婚経験があり、元配偶者との間に子どもがいる場合も、戸籍謄本には記録されているため、見逃す心配はありません。
ただし、被相続人のあらゆる戸籍謄本を収集するためには、手間も時間も要することから、弁護士に依頼することも方法のひとつです。
STEP
03
14日以内
- 「国民健康保険被保険者証」を返却する
- 「介護保険被保険者証」を返却する
- 「世帯主変更届」を提出する
相続財産を調査・確定する(財産目録を作成する)
相続人が確定したら、相続財産を調査します。相続財産は現金や預金、有価証券、土地、家屋など金銭に換えられる財産が該当します。一方で、未払いの住宅ローンや固定資産税、社会保険料などの債務も含まれるため注意が必要です。仮に、これらの財産や債務に漏れがあった場合、遺産分割や相続税申告をやり直さなければいけません。相続財産を調査した結果は、財産目録としてまとめれば、遺産分割協議を行う際に重要な資料として活用できます。
STEP
04
3ヶ月以内
- 単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかの中から選択する
- 相続放棄または限定承認を選択した場合、期間を伸長する
STEP
05
4ヶ月以内
- 被相続人の所得税の準確定申告をする
遺産分割協議を行う
遺言書がない場合は、被相続人が残した相続財産の分け方について相続人同士で話し合う必要があります。その場を遺産分割協議と言い、すべての相続人が参加しなければ法律上、有効と判断されません。話し合った結果は、遺産分割協議書として書き残すことで、後に相続人同士のトラブルを避けられます。
法律では、相続財産の分け方についての期限は定められていませんが、相続税を申告する際に遺産分割協議書が必要になるため、それまでに終えると良いでしょう。
STEP
06
10ヶ月以内
相続税を申告、納税する
相続税の申告は、相続の開始を認識した日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。相続税の申告先は、被相続人の居住地を管轄する税務署です。申告を怠った場合、無申告加算税や延滞税などの過料を科される恐れがあります。
相続税を申告する際は、以下の書類が必要です。
- 戸籍謄本
- 遺産分割協議書の写し
- 相続人すべての印鑑証明書
- 残高証明書(預貯金、借入金など)
- 支払証明書(生命保険金、退職手当金など)
- 不動産の登記簿謄抄本(登記事項証明書)と地形図
- 固定資産税評価証明書
相続税の申告を終えたら、納税を行います。以下の納税方法があるため、この中から自身に最適なひとつを選ぶと良いでしょう。
- インターネット
- クレジットカード
- 税務署または金融機関の窓口
Knowledge金沢市・かほく市~白山市エリアで、
不動産相続について相談するなら、
かなざわ相続の窓口

かなざわ相続の窓口は、金沢市を中心に、かほく市、野々市市、白山市、津幡町、内灘町に密着して、不動産相続を手掛けている不動産会社です。当窓口は司法書士や行政書士、土地家屋調査士、税理士などの専門家と連携しており、生前から相続後までの対策をトータルでサポートできます。不動産に相続についてお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。