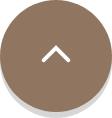目次

将来に備えて
相続対策を進める
相続財産の中でも不動産は高額である場合がほとんどです。そのため、財産を所有する方は、相続人が金銭的にも精神的にも大きな負担にならないよう、早くから相続対策を進めることが大切です。こちらでは不動産の相続対策について、いつから始めると良いか、生前贈与の有効性やそのメリット、注意点などについて紹介します。
Gift思い立ったが吉日!
不動産の相続対策は
早くから始めることが大切です

財産を所有している方は「いまのところ元気だから」という理由で、相続に関することを先延ばしにしていませんか。不慮の事故で亡くなるなど、相続はいつ発生するかわかりません。認知症の発症によって正常な判断ができなくなると、相続に関することも含めてあらゆる手続きが難しくなるケースもあります。
また、遺言書の作成や生前贈与の実施は、存命のうちに行わなければ、法律上、すべて無効になります。こうしたことから、不動産の相続対策は元気で判断力があるときに、進めるのがベストなタイミングと言えます。
Gift始めるなら、今!
認知症前の相続対策

法律上、認知症を患っている方による契約行為はすべて無効になるため、預金の引き出しや解約、契約行為、不動産の売買、相続税対策、遺言書の作成、遺産分割の検討ができなくなります。こちらでは、財産を所有している方が認知症になってしまった場合に備えて、財産管理や契約行為を代理で行ってもらうための「家族信託」「成年後見人制度(任意後見)」について紹介します。

家族信託とは?
家族信託は、自身の財産を信頼できる家族に託し、その管理、処分を任せる制度です。この制度を活用することで、自身に代わって信頼できる家族が不動産の売買契約や賃貸借契約を結べるようになります。ただし、判断力がある状態でなければ、家族信託の手続きを行えません。認知症が軽度であれば、手続きを進められる可能性もありますが、症状が急速に進行するケースもあるため、できる限り早く準備を進めましょう。

成年後見人制度(任意後見)とは?
成年後見人制度は、自身が認知症や精神障がいなどで判断力が低下した方のために、サポート役を選任する制度です。選任された後見人は、自身に代わって財産管理や契約締結などを任せられるようになります。
成年後見人制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。法定後見制度は、すでに判断力が低下している方の後見人を選定する制度です。任意後見制度は判断力のある方が信頼できる家族などを後見人として指名する制度になります。将来の財産管理に不安がある場合は、元気なうちに任意後見制度を活用しておくと安心です。
「家族信託」と「成年後見人制度(任意後見)」の違いについて
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 家族信託 | 成年後見人制度(任意後見) | |
|---|---|---|
| 権限 |
|
|
| 代理権限の有無 |
|
|
| 権限の開始時期 | 信託契約の締結時点 | 原則、委任者の判断力が低下した時点 |
| 家族だけで財産管理をできるか | 信託契約の範囲内であれば、家族(受託者)だけで自由に財産を管理できる | 家族だけで財産管理はできない。家庭裁判所の監督を受けて財産を管理する |
| 費用 |
|
|
Gift不動産の生前贈与は、
相続税を減らすカギになります

土地や建物などの不動産がある場合、相続人に対して高額な相続税が発生する恐れがあります。そのようなケースを避けるために、「生前贈与」の活用を検討しましょう。
生前贈与とは、相続が始まる前に財産を別の人に譲る方法です。不動産を生前贈与した場合、相続税を抑えられるだけでなく、さまざまなメリットがあります。相続税対策は、現状把握で半年、その後、法定相続人との話し合いを重ねて具体的な対策に着手するまでに1年以上かかることもあるため、早めに進めていくことが大切です。
生前贈与にはさまざまなメリットがあります!
①相続税の軽減効果がある
相続税は、相続した際の課税遺産総額に対して課される税金です。生前贈与によって、自身の財産を減らすことで、課税対象額を抑えられます。また、相続税は基本的に基礎控除額を上回った分に対して課されるため、生前贈与によって相続財産が基礎控除額を下回るか、同等になった場合は相続税が課されません。
②贈与税を減らす累積効果がある
贈与には、相続と同じく基礎控除があります。贈与の課税方式は2通りあり、「暦年課税」では、年間の基礎控除額は110万円です。つまり、1月1日から12月31日までの贈与額が1人当たり110万円以下であれば、贈与税はかかりません。贈与税は年単位で清算されるため、毎年贈与を積み重ねることで、より大きな節税効果を得られるでしょう。
③税制改正による不利益を回避できる
税法の改正や特例制度の廃止などによって、現在の相続税や贈与税の優遇制度がこの先も続くとは限りません。相続や贈与についての税制変更によって、自身が想定していた節税効果を得られなくなる恐れもあります。税制の改定によって不利益を受けないためにも、早めに生前贈与を進めることが大切です。
④贈与時期を選択できる上、評価額が上昇した場合の影響を受けない
生前贈与は、自身で贈与するタイミングを自由に選択できる点も大きな魅力です。不動産や有価証券などの財産は、時期によって評価額が変動します。将来的にそれらの価値が上昇する見込みがある場合、評価額が低いうちに贈与することで、相続税を抑えられるのです。税法上、相続開始から遡って3年間分は相続財産と見なされますが、評価額は贈与時のものになり、上昇の影響を受けないため、相続税の節約につながります。
⑤希望する人に財産を引き継がせやすい
相続の場合、遺言書に相続させたい人を書き記すことはできますが、それに納得しない相続人がいれば、不服を申し立てられる可能性があります。一方、生前贈与では、自身が希望する人に財産を渡しやすくなります。仮に、生前贈与で引き継いだ財産が法定相続人の遺留分を侵害していた場合、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求されても、贈与した財産の所有権の保持が可能です。
生前贈与の注意点について
生前贈与を行う際の注意点として、以下の3つが挙げられます。
「名義預金」と見なされるケース
財産を引き継ぐ方に知らせずに、その方の名前で口座を開設して預金していた場合、相続税を課される恐れがあります。そのため、贈与契約書を作成して、贈与の事実を明確にしておくことが大切です。
特定の人に偏った贈与をしたケース
このような相続では、不利益を被る法定相続人が出てしまいます。その相続人が「遺留分侵害額請求」を行った場合、不利益分に相当する金銭の支払いを請求されることもあるため、贈与は慎重に進めましょう。
財産を所有する方の生活資金
自身の寿命は予測できないため、老後の生活費や介護費用はしっかり確保することが大切です。贈与で財産を譲り過ぎた結果、自身の資金が不足して家族や親族に負担をかけてしまう恐れがあります。贈与は、老後の資金計画を踏まえて行いましょう。
Gift金沢市・かほく市~白山市の相続・生前贈与は
かなざわ相続の窓口へご相談ください

かなざわ相続の窓口は、創業以来、金沢市、かほく市、野々市市、白山市、津幡町、内灘町に密着して不動産相続を手掛けてきました。当窓口は、司法書士や行政書士、土地家屋調査士、税理士などの専門家と連携。不動産の相続や売却については、不動産のプロと専門家によるダブル体制で、しっかりサポートいたします。不動産についてのご相談は、かなざわ相続の窓口までお問い合わせください。